研 究 概 要
最近、アゾベンゼンクロモフォアを有する高分子薄膜にレーザー光の二光波を干渉露光することにより、薄膜表面に干渉縞に対応する凹凸のレリーフ(表面レリーフ回折格子:SRG)が形成される現象が注目を集めています。この現象は、アゾベンゼンのtrans-cis異性化反応に基づくフォトクロミック反応に伴って数百nmからmmスケールの物質移動が誘起される現象で、基礎科学の観点から興味深いだけでなく、書き換え可能なホログラムや光導波路カップラーなど、フォトニクスへの応用の観点からもたいへん興味がもたれています。SRG形成のメカニズムについて、いくつかのモデルが提案されていますが、まだ詳細は明らかになっていないのが現状です。現在行われている光誘起物質移動現象の研究は、主に高分子系材料が対象となっていますが、私は、低分子系材料を用いて以下の研究を進めています。
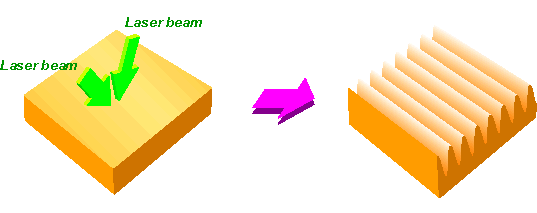
[ 図の説明 ] 光誘起表面レリーフ回折格子 (SRG) 形成:アゾベンゼンクロモフォアを有する高分子の薄膜にレーザー光を干渉露光すると(左)、薄膜表面に干渉縞に対応する凹凸のレリーフが出来る(右)
1.アゾベンゼン系フォトクロミックアモルファス分子材料を用いる光誘起SRG形成
フォトクロミックアモルファス分子材料(室温以上で安定なアモルファスガラスを容易に形成する低分子系フォトクロミック材料:下記5参照)は、分子構造が明確で、かつ、分子鎖のからまりあいの効果がないことから、高分子と比べてよりシンプルな系を与え、分子構造とSRG形成能との相関の検討をより容易にすると考えられ、メカニズムの解明に有利であると期待されます。このような観点から、アゾベンゼン系フォトクロミックアモルファス分子材料を用いる光誘起SRG形成の研究を行っています。これまでに、高分子鎖の存在しないフォトクロミックアモルファス分子材料が、SRG形成用の優れた材料の候補となることを示すとともに、ガラス転移温度の高い材料を用いる方がSRG形成に有利であること、異性化に必要な体積が大きくなるとSRG形成に不利になることを示しました。さらに、フォトクロミックアモルファス分子材料と同じ骨格を側鎖に含むアモルファス高分子を新たに合成し、それらのSRG形成をフォトクロミックアモルファス分子材料と比較・検討することによって、アモルファス分子材料がアモルファス高分子に比べてSRG形成速度が速いことを明らかにしています。
また関連する現象として、フォトクロミックアモルファス分子材料を用いて作成したマイクロファイバーの光屈曲挙動を検討し、このファイバーが光照射に伴って屈曲するフォトメカニカル効果を示すこと、この際、照射する光の偏光方向を変えると、屈曲方向が異なることを明らかにし、この現象が光誘起物質移動現象と関連していることを示唆する結果を得ています。
(参考論文)
Adv. Mater., 14, 1157 (2002); Opt. Mater.,
21, 249 (2003); Chem. Lett., 32, 710
(2003); Chem. Lett., 33 (9), 1152-1153 (2004); J. Mater.
Chem., 18, 242 (2008); Mater. Chem. Phys., 113, 376 (2009); J. Mater. Chem., in
press (2010).
2.アゾベンゼン系有機単結晶を用いる光誘起SRG形成
これまでの光誘起SRG形成の研究対象は、アモルファス高分子、高分子液晶、および上述のアモルファス分子材料に限られていました。これに対し、単結晶の表面でSRG形成が可能であれば、そのSRG形成能を分子構造や結晶構造と相関させて検討することにより、SRG形成機構に関する新たな重要な知見が得られると期待されるだけでなく、SRG形成に与える分子の周囲の環境の影響など、さまざまな新しい知見が得られると考えられます。
このような発想から、ごく最近、4-(dimethylamino)azobenzene (DAAB) の単結晶を用いるSRG形成の検討をおこない、単結晶表面にもSRG形成させることが可能であることを世界に先駆けて実証するとともに、SRG形成が光照射する際の結晶の配向に大きく依存すること、SRG形成の書込光偏光依存性がアモルファス系とは全く異なることを明らかにしました。また、DAAB以外のいくつかのアゾベンゼン系誘起単結晶においても光誘起SRG形成が可能であることを確認しており、アゾベンゼン系有機単結晶表面における光誘起SRG形成が一般的な現象であることを示しています。
![]() 科研特定「フォトクロミズム」News
Letter Vol.4 に詳細記事(こちら)
科研特定「フォトクロミズム」News
Letter Vol.4 に詳細記事(こちら)
(参考論文)
Appl. Phys. Lett., 87, 061910
(2005); 88th Annual Meeting of JCS, 3L7-39 (2008); 57th SPSJ Annual
Meeting, 1Pc129 (2008); J. Phys. Chem. C., 112, 16042 (2008).; ChemPhysChem, 9, 2174 (2008).
以上の、光誘起SRG形成に関する研究のほかに、これまで、光・電子機能を有する有機化合物群に興味をもって、新しい分子・物質群の設計・合成と、それらの構造・物性・機能の解明および応用に関するさまざまな研究を進めてきました。以下に、その概要を示します。
3.導電性有機錯体の開発研究
分子内に多数のカルコゲン原子を有する一連の新規テトラチアフルバレン誘導体を設計・合成し、これらのさまざまな電荷移動錯体ならびにイオンラジカル塩を調製しました。また、それらの導電性を調べ、いくつかのイオンラジカル塩が極低温まで金属的挙動を示すことを見出しました。さらに、これらの結晶構造を明らかにし、構造と導電性との相関について知見を得ました。
4.アモルファス分子材料の設計・合成
アモルファス分子材料(室温以上で安定なアモルファスガラスを容易に形成する低分子系有機化合物群)の創製を目的として、一連の新規p電子系化合物群を設計・合成しました。また、それらの分子構造とガラス形成能・モルフォロジー変化との相関を検討し、アモルファス分子材料創製のための分子設計指針を示しました。さらに、熱力学的非平衡状態であるアモルファスガラスからの緩和過程を検討し、アモルファス分子材料の多くが、ガラス状態のほかに複数の結晶形態をとるポリモルフィズムを示すことを明らかにするとともに、ガラスを昇温していく際の段階的な相転移の様相を明らかにしました。
5.フォトクロミックアモルファス分子材料の創製 ![]() 詳細はこちら
詳細はこちら
フォトクロミック特性を有するアモルファス分子材料(フォトクロミックアモルファス分子材料)の概念を提出し、その概念に基づいて、アゾベンゼン系ならびにジチエニルエテン系フォトクロミックアモルファス分子材料を創製するとともに、これらのアモルファス薄膜におけるフォトクロミック特性を明らかにしました。
6.その他
上述のほか、新規有機非線形光学材料、低分子系有機ゲル、新規オリゴチオフェン誘導体などの設計・合成と、物性研究を行ってきました。
(背景撮影:H21.9.1 新潟付近上空より富士山北壁を望む)